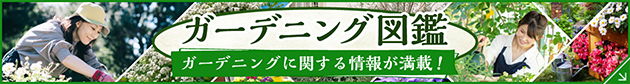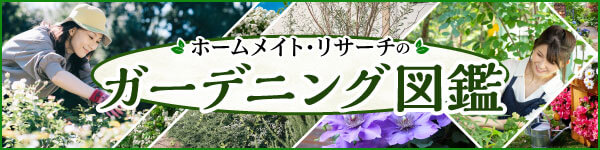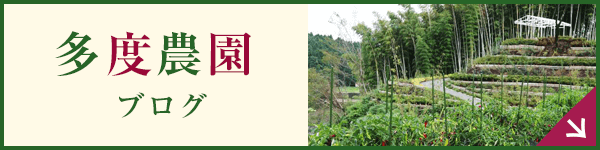植物園情報
アジサイ/ホームメイト
| 科名 | アジサイ科 |
|---|---|
| 属名 | アジサイ属 |
| 原産地 | 日本 |
| 栽培の難易度 | 初心者向け |
|---|
| 植物分類 | 低木 |
|---|---|
| 草丈 | 1~1.5m |
| 開花時期 | 5~7月 |
| 花もち | 1~2週間程度 |
| 花色 | 赤、ピンク、青、 紫など |

| 耐暑性 | やや弱い |
|---|---|
| 耐寒性 | 普通 |
日本が原産のアジサイは、7世紀後半から8世紀後半にかけて編纂された万葉集や、平安後期の短歌に詠まれるなど、古くから知られている草花です。現代では、母の日のプレゼント用としてホームセンターの園芸コーナーなどに並んでいますが、これらのアジサイは、医師であり植物学者であるシーボルトによってヨーロッパに伝えられた品種が改良され、日本に逆輸入されたもの。「西洋アジサイ」や「ハイドランジア」と呼ばれる品種です。
シーボルトは、オランダ商館の医師として江戸時代に長崎の出島へやってきました。日本人医師を育成する傍ら、自然科学の研究にも情熱を注ぎ、数多くの植物を採取して調査するなどして、オランダに持ち帰った経緯があります。シーボルトが特に興味を持ったのがアジサイで、日本人妻のオタキさん(楠本滝さん)の名前から「ハイドランジア オタクサ」という学名を付けたと言われているほどです。なお、この学名は、シーボルトが発表する前に「ハイドランジア マクロフィラ」という学名で発表されていたため、認められませんでした。
アジサイの特徴は、土壌の酸性度によって花色が変わることです。酸性の土壌では花色が青くなり、アルカリ性の土壌では赤くなります。市場に出回っているアジサイは、その性質を利用し、酸度調整された西洋アジサイの鉢花です。
ガーデニング年間スケジュール
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 植え付け | ||||||||||||
| 施肥 | ||||||||||||
| 切り戻し | ||||||||||||
| 開花 |
育て方のポイント

アジサイは、種から育てることができますが、苗木を植えて育てるのが一般的です。
アジサイを育てる環境は、西日が当たらない半日陰の場所が適しています。日陰でも育ちますが、花付きが悪くなってしまうので注意しましょう。
土質は、水はけが良く保水性のある土が最適です。
地植えの場合は、苗木を植え付けたらたっぷりと水やりをし、根付いたあとは、特に水やりの必要はなく、夏場に土の表面が乾いているようなら、水やりをします。
鉢植えの場合は、苗木を植え付けたらたっぷりと水やりをし、根付いたあとは土の表面が乾いたら、鉢底から水が流れ出すまで与えるようにしましょう。アジサイは水切れに弱い性質があります。特に鉢植えで育てる場合は注意が必要で、乾燥したままにすると葉が萎れて、枯れてしまうことがあります。乾燥しやすい夏場は、1日2回、水やりをするようにしましょう。
植え付け
土作り
市販のアジサイ用の土か、赤玉土(小粒)と腐葉土、及びピートモス(※)を、5:3:2の割合で配合した用土が適しています。アジサイを青色にしたいなら土を酸性に、ピンクや紅色にしたいならアルカリ性の土質にしましょう。
※ピートモスとは、水気の多い場所で育ったコケ類を、細かく砕いて乾燥させた土のこと。
植え付け
アジサイの苗木を植え付ける適期は、12~3月です。
アジサイを地植えする場合は、根鉢の大きさよりも2~3倍の植え穴を掘って植え付けます。
鉢植えの場合は、苗木よりも一回り大きな鉢に植え付けます。鉢は、保水性のある磁器がおすすめです。またアジサイは、横に根を張る性質があるので、横長で深めの鉢が良いでしょう。
増やし方(挿し木)

挿し木で増やせます。挿し木は、3~4月に前年の枝を用いて行う春挿しか、6月に当年の枝を使って行う夏挿しができます。
挿し木をする場合は、花芽の付いていない枝の先端を15cmくらいにカットし、30分ほど切り口を水に浸けておきます。市販の挿し木用培養土を入れた鉢に2cmほど挿し、半日陰の場所で育てましょう。
手入れ
水やり
地植えの場合、水やりは不要です。ただし、日照りが続いたときや、日がよく当たる場所で乾燥しやすい場合は、土の様子を見て水を与えましょう。
施肥
施肥は年に3回、三大要素が均等に含まれたタイプの肥料を与えます。
1回目の施肥は3~4月で、2回目は花後の7月です。
3回目の施肥は、12月と1月に1回ずつ行いましょう。
花後は、10日に1回の頻度で「薄い液肥」を与えると、生育が良くなります。
切り戻し
剪定は、1年に2回行います。
1回目の剪定は、花が咲き終わった7月に、花から2~4枚下の葉の位置で枝を切り詰めます。
2回目は、来年の花芽ができる10月です。花芽が目視できる大きさに育っていることを確認し、花芽を残すように「内向きの枝」、「下向きの枝」、「伸びすぎている枝」、「細い枝」を選んで、付け根から切り取ります。
その他
背が高くなりすぎた場合は、数年に1回、枝の付け根に近い部分で切る強剪定をします。