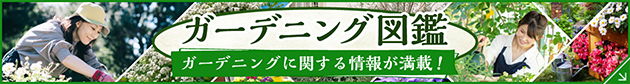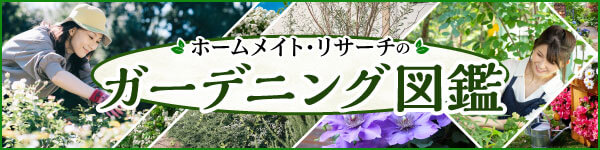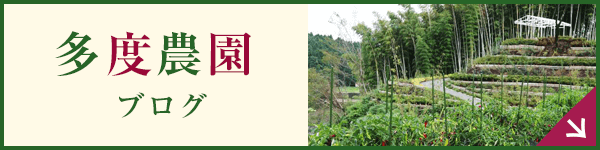植物園情報
ヒガンバナ/ホームメイト
| 科名 | ヒガンバナ科 |
|---|---|
| 属名 | ヒガンバナ属 |
| 原産地 | 中国 |
| 栽培の難易度 | 初心者向け |
|---|
| 植物分類 | 多年草 |
|---|---|
| 草丈 | 20~50cm |
| 開花時期 | 9月 |
| 花もち | 1週間 |
| 花色 | 赤、白、ピンク、 黄、オレンジなど |

| 耐暑性 | 強い |
|---|---|
| 耐寒性 | 強い |
ヒガンバナは中国が原産で、約2500年前に日本に伝わったとされていますが、はっきりとしたことは分かっていません。日本では、あぜ道や土手、寺院、墓地など、人が生活する範囲に自生しています。東京の「国営昭和記念公園」や埼玉県の「巾着田」などの観光名所では、絨毯のように咲いているヒガンバナの風景が有名です。
ヒガンバナは、昔は縁起が悪い花として、庭に植えたり生け花などで使ったりしてはいけないとされていました。近年では、花の美しさや育てやすさから、欧米で「リコリス」という名前で人気があり、日本でもリコリスの球根が流通しています。
ヒガンバナは、秋になると花茎を長く伸ばして、先端に5~8輪の花を咲かせます。花が咲き終わると花茎が倒れ、地際から葉がでてきて、生長しながら冬越しします。春になると葉を枯らして休眠に入るというサイクルで生長します。
ヒガンバナの特徴は、放射状に広がる細い花弁です。ヒガンバナの花弁と言えば赤色のイメージですが、品種改良によって白や黄、オレンジ、ピンク、紫などの花色をしたヒガンバナも流通しています。
ヒガンバナの名前「彼岸花(ヒガンバナ)」は、お彼岸の頃に花が咲くことが由来です。また、「曼珠沙華(マンジュシャゲ)」という別名もあり、サンスクリット語で「赤い花」を意味します。
なお、ヒガンバナには有毒物質の「リコリン」という「アルカロイド」の一種が含まれているため、口に含むと中毒症状が現れます。
ガーデニング年間スケジュール
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 植え付け | ||||||||||||
| 施肥 | ||||||||||||
| 切り戻し | ||||||||||||
| 開花 |
育て方のポイント

ヒガンバナは日当りが良い場所か、半日陰の場所で育てます。
また、水はけが良い土壌を好みますが、極端に乾燥すると育たず、花付きが悪くなるので注意しましょう。
ヒガンバナは耐寒性があるため、防寒対策をしなくても冬越しさせることができます。ただし、寒冷地では株元に藁や腐葉土などで覆ってマルチングし、防寒対策をしましょう。
植え付け
土作り
地植えの場合は、水はけの良い土であれば、特に選ばずに育ちます。水はけが悪いようであれば深さ30cmほど土を掘り上げ、掘り上げた土に対して3割程度の腐葉土を混ぜ込みましょう。
鉢植えの場合は、市販の草花用培養土を使うか、赤玉土(小粒)と腐葉土を7:3の割合で配合した用土を使用します。
植え付け
ヒガンバナの植え付け時期は、7~8月です。
地植えの場合は、球根1個分の深さに植え付けます。複数の球根を植え付ける場合は、20~30cmの株間を空けましょう。
鉢植えで育てる場合は、5~6号鉢に1~3球を目安に植え付けます。鉢底ネットを敷き、軽石を1~2段分入れたら、鉢の縁から2~3cm下の高さまで用土を入れます。球根の頭が用土の表面に隠れるくらい浅く植え付けましょう。
増やし方(分球)
ヒガンバナは分球で増やします。分球の適期は、6~8月です。
株が混み合ってきているようなら球根を掘り上げ、子球を離して植え付けましょう。
なお、子球は植え付けてから花が咲くまで2~3年かかります。
手入れ
水やり
地植えの場合は、植え付けてから根付くまではたっぷりと水やりをします。その後は降雨のみで大丈夫ですが、乾燥した日が続いたら水やりをしましょう。
鉢植えの場合は、植え付けてから根付くまではたっぷりと水やりをします。その後は土の表面が乾いたらたっぷりと水やりをしましょう。
施肥
花が咲き終わって葉が茂っている10月頃に、少量の「化成肥料」を施して、球根を太らせます。リン酸やカリ分が多めに配合された肥料を与えると、根の発育も促すことができます。
切り戻し
咲き終わった花は、花房の下で切り取ります。咲き終わった花を残しておくと腐って、病気を招く原因になるので、早めに切り取りましょう。