冬の植物園[ガーデニング]情報
冬に行く植物園!人気スポットを調査しよう
冬は外出するのも億劫になりがちですが、家族でのお出かけや恋人とのデートは大切な時間。一年中美しい草木や花たちを鑑賞できる植物園は、冬に出かけたい人気スポットのひとつです。草花やイルミネーションに癒され、大切な人との時間とゆっくり楽しめる植物園の人気スポットをご紹介します。
冬でも暖かい温室が魅力の植物園
古い歴史を持つ「京都府立植物園」の温室

冬のお出かけに植物園をおすすめするひとつの理由が温室です。熱帯地域の植物を管理・展示する温室に足を入れると、南国を訪れたような暖かさに包まれて外の寒さを忘れてしまう程。日本の植物園の中でも古い歴史を持つ「京都府立植物園」も、複数のゾーンを持つ温室を備え、回遊式の順路を進みながら様々な植物を観賞できるようになっているのです。気候別に区分けされている各ゾーンには、国内で初めて展示される植物も多くあり、普段は見られない植物や珍しい花々など世界中の熱帯植物を観察しながら楽しめます。また、温室内の「特別展示室」では一年を通して各種展示会も開催。冬の約200鉢もの「洋ラン展」は見応え抜群の展示も見逃せません。
5つの温室が楽しめる「東山動植物園」
愛知県名古屋市にある「東山(ひがしやま)動植物園」にある温室は、1937年(昭和12年)から公開された「前館(ぜんかん)」と1960年(昭和35年)から順次開設された「後館(こうかん)」を持ち、「前館」は国の重要文化財にも指定されています。「前館」は全面ガラス張りで全長66m、最高高さ12.4mにも及び、“トラス構造”と呼ばれる鉄骨造が特徴的です。「後館」は「前館」に比べてがっしりとした造りが印象的。「中南米産植物温室」や「ハワイアンハウス」、「水生植物室」、「サンギャラリー」といった5つの温室から構成され、様々な種類のサボテンやブーゲンビレア(ブーゲンビリア)、ハイビスカスや水生植物などを鑑賞できます。
冬のイルミネーションが楽しめる植物園
クリスマスシーズンに楽しめる「京都府立植物園」のイルミネーション
植物園で冬に開催されているイルミネーションも、多くの人が足を運ぶ人気のイベントです。「京都府立植物園」ではクリスマスシーズンとなる期間に、LEDによるイルミネーションイベントを開催しています。装飾されるのは、正門から「観覧温室」、「北山(きたやま)門」と「賀茂川(かもがわ)門」までの樹木や園路、花壇など。20mもの高さがあるトウカエデの装飾が、すぐそばの池に反射される様子は美しく、きらめく噴水と一緒に闇の中で幻想的な雰囲気をかもし出します。イルミネーション期間中は、通常夕方で閉室する「観覧温室」が夜間開室され、「ジャングル室」や「砂漠サバンナ室」の夜の表情も見どころです。
「アイスチューリップ」が見どころ!「長居植物園」のイルミネーション
大阪市にある「長居(ながい)植物園」でも、冬になると、園内全体に大規模なイルミネーションが施されます。大きな見どころは冬に花を咲かせる「アイスチューリップ」。冷たい空気の中、イルミネーションの輝きとかわいいチューリップが共演する姿は他では見られません。2016年(平成28年)のイルミネーションでは「光の森」をテーマとし、7色に輝くハートのトンネルや並木道のライトアップ、クリスマスツリーのイルミネーションなど、園内のいたる所で幻想的な輝きが見られました。どのような輝きに出会えるか、冬の「長居植物園」に注目してみましょう。
冬のデートスポットとして利用できる植物園
大人デートが楽しめる「小石川植物園」
冬の植物園は、恋人とのデートにも人気のスポットです。東京都にある「小石川植物園」は、国指定名勝のひとつで、都心にいることを忘れる程の美しい景観に出会えるのが魅力。園内は多くの木々に囲まれ、春から冬まで一年中様々な花を愛でることができます。20品種のツバキを管理するツバキ園では冬に開花時期を迎え、11~4月までそれぞれに美しさのあるツバキの花々に飽きることがありません。ツバキの花をしっとりと鑑賞しながらまわる冬の「小石川植物園」は、大人のデートにおすすめの場所です。
一日中楽しめる「アロハガーデンたてやま」
千葉県館山市にある「アロハガーデンたてやま」も、冬のデートに欠かせない人気スポット。「連続温室や大温室」を備え、ハイビスカスやブーゲンビレア(ブーゲンビリア)など南国の花々を楽しむことができます。さらに、動物と触れ合える「動物広場」や、フラダンスのショーが開催される「フラテラス」など、南国の植物以外にも見どころが多いのが魅力。デート中は園内でハワイアンフードを味わえるレストランやカフェで休憩したり、「マルシェ」や「アロハ雑貨店」で買い物を楽しんだりと、一日いても飽きることがありません。



冬には冬ならではの植物や自然とのふれあいが楽しめます。またこの季節を代表する鮮やかな花があることも見逃せません。百花繚乱(ひゃっかりょうらん)の春や夏、紅葉が美しく実りの多い秋とはまた違った、寒い季節にふさわしい自然の楽しみ方を見付けてみてはいかがでしょう。
冬の植物園でバードウォッチング
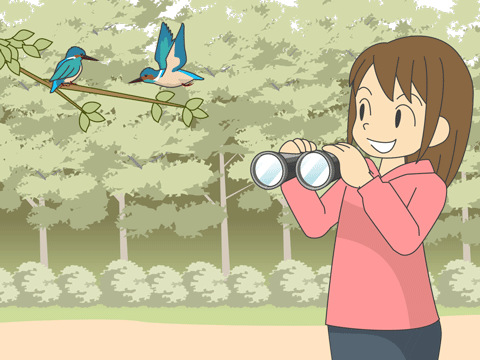
日本には北海道から沖縄までたくさんの植物園があり、その多くは都市部からの距離もそれ程離れていないため、多くの人々が休日に一日を過ごすことに適しています。また、国立大学などの教育研究機関が学術探求のために設置した植物園や薬用植物園もありますが、大半の植物園は市民のための公園としての意味合いが強く、レジャーとして自然を楽しむことを目的としているケースが目立ちます。つまり、都市で生活している一般市民でも気軽にその季節ごとの自然を楽しむことができるのが、植物園の大きな魅力であると言えるのです。
「植物園」という名を冠しているものの、植物園で触れ合うことのできる自然は植物だけでなく、その周りの風景や環境、季節ごとの風や日照の違い、森で生活するあらゆる生物たちの観察など多岐に亘ることは言うまでもありません。落葉樹の葉が落ちた冬には、鳥たちを観察する楽しみがあることも忘れてはならないでしょう。葉が生い茂っていた季節には見ることが難しかった梢の上の鳥などは、落葉樹が枯れ木となる冬には観察がよりしやすくなります。また、植物園内の池や沼などの水辺も、冬にやってくる鳥たちを見るには適しています。植物園によってはその園で見ることのできる野鳥が明示されている説明板などが設置されていますので、それを参考に鳥を探して歩くのも楽しいものです。
ポインセチアはクリスマスフラワー
クリスマスをイメージさせる色と言えば、「赤と緑」と答える人は多いのではないでしょうか。11月から12月にかけて色づき、まさに「赤と緑」の鮮やかな彩りが美しいポインセチアは、その季節と色合いから別名「クリスマスフラワー」とも呼ばれています。このポインセチアの赤い部分は、実は花ではなく、つぼみを包んでいる「苞葉(ほうよう)」と呼ばれる葉です。花は茎のてっぺんにある粒状の物で、花びらを持っていないのが特徴です。
ところで、ポインセチアはメキシコが原産の花で、日本には明治時代に入ってきたと言われています。その赤い色から空想上の大酒飲みの生き物「猩々(しょうじょう)」に似ていることから、この花の和名は「ショウジョウボク(猩々木)」と名付けられました。現在でも正式名称はショウジョウボクのポインセチアですが、大酒飲みに例えられる時代があると思えばクリスマスシーズンを彩る花として人気が高まる時代もあるところが、面白いと思いませんか。
冬の終わりの黄色い花・ロウバイ
冬には花を咲かせる木々が少ない中、12月から2月にかけての晩冬の時季に黄色い花を咲かせるのが、ロウバイ(蝋梅)です。梅の花のようにも見えるために名前にも「梅」の字が用いられていますが、ウメの仲間ではなくクスノキ目に分類されています。中国が原産の木で、日本には江戸時代に入ってきて以来、庭木としても生花としても愛されており、非常に良い香りを発することでも親しまれている花です。やや半透明で鈍い光沢の黄色い花は、寒々しい冬の景色の中において美しい差し色となることもあり、冬の季語にも選ばれています。
日本国内の植物園や庭木で最も多く見られるのは、「ソシンロウバイ(素心蝋梅)」と呼ばれる園芸品種です。ロウバイの花にある芯部分が暗い紫色であるのに対してソシンロウバイは花全体が黄色く、より鮮やかな印象を受けます。そして香りもロウバイに比べて強いため、咲いた頃に気づく人も多いことでしょう。
ロウバイの花のあとでウメが咲き、サクラが咲き、春になっていきます。つまり冬の終わりを告げ、春の到来の始まりを教えてくれる花がロウバイなのです。
咲く花が少ない冬の時期ですが、温室のある植物園なら季節に関係なく、いつでもいろいろな花を見ることができます。自宅でガーデニングや家庭菜園をする場合でも、温室があると寒さから苗や芽を守ることができ、発育にも効果的です。
熱帯植物園に行こう

寒い時期の植物園は花が少なく、見どころも少ないですが、熱帯植物園なら冬でもいろいろな花が咲き、目を楽しませてくれます。園内も快適な温度に保たれているので、コートを脱いで軽装で歩き回れるのも嬉しいポイントです。ハイビスカスやブーゲンビリア、エンゼルトランペットなどは、色も鮮やかで園内でもひときわ目立ち、通年見られるので、いつ訪れても南国気分を味わうことができます。
主な熱帯植物園として、東日本では、函館市営熱帯植物園(函館市)や下賀茂熱帯植物園(南伊豆町)、新潟県立植物園などが、また、西日本では手柄山温室植物園(姫路市)、松江フォーゲルパーク(松江市)などが温室設備を備え、熱帯・亜熱帯の花の種類も充実しています。こうした熱帯植物園の中には、日本で見られない植物も多く、珍しい花や樹木を栽培しているところも多くあります。また、バナナやマンゴーなど普段見慣れているトロピカルフルーツが、どのような木に実を付けているのかも知ることができ、食育のための学習としても最適です。
ちなみに、冬はポインセチア、シクラメン、シンビジュームやデンドロビュームなどの洋ランの仲間がこの時期に見頃を迎えます。どの花もお馴染みの花で、一度は目にしたり耳にした人も多いでしょう。
園内には、飲食店やお土産コーナーも完備されているので、冬休みのデートや行楽には、意外な穴場スポットかもしれません。
温室を作ろう
冬は気温が下がり、空気も乾燥するため植物の生育にはマイナス条件が多くなります。中でも、春植えの野菜の苗を育てるには、発芽するためにある程度の温度が必要になります。そこで、植物が育つ環境を少しでも良くするために温室を作ってみましょう。
温室は規模や使う材料によって、費用も大きな差があります。家庭菜園や小さなスペースの栽培であれば、園芸店やホームセンターなどで市販されているビニール温室を利用しても良いでしょう。簡単に組み立てることができ、育苗や小さな花の苗であれば十分で、費用も数千円程度で完成します。ただし、縦型のものは風の影響を受けやすいので、倒れないように固定しておくようにすることが大切です。
地植えの野菜や花などは、園芸店で半円状の支柱を購入し、テントを張る要領で数本を組み合わせて縛ります。支柱を埋めた部分はしっかりと地固めをして、支柱の先が土から出ないようにします。組んだ支柱の上からビニールシートを張り、ビニールシートの端を土の中に埋めれば完成。こちらも風に飛ばされないよう、石などで重しを置いて固定します。
温室で育てれば、発芽温度も確保できる他、発芽後も野鳥などから苗を守ることができます。小春日和の暖かな冬の一日を利用して、オリジナルの温室を作ってみませんか。
ウメの観賞
2月4日の立春。暦上では春ですが、外はまだ寒空が広がります。それでも2月中旬を過ぎるとポツポツとウメの花がほころび始め、春が近いことを告げます。
梅は古くから日本人に愛された花で、日本の文化や生活に大きく関係してきました。古代の日本ではサクラよりウメが愛好され、和歌や書画にも多くの作品が残っています。また、菅原道真がこよなく愛した花とあって、全国の天満宮には梅の木が植えられ、福岡県の太宰府天満宮や京都府の北野天満宮など、梅の名所となっているところも多くあります。
全国各地には梅林公園があり、2月から3月にかけてウメの花が見頃を迎え、開花に合わせて梅まつりも開かれます。サクラほど派手さありませんが、紅色や白い花を付けた可憐な花は、奥ゆかしく優雅で趣のある風情を感じます。ウメの種類は500種以上あると言われ、各地で見られるウメの花も様々。梅林公園でゆっくり梅を観賞し、もうすぐやって来る春の気配を感じてみましょう。
冬は花を咲かせる植物が少なく、庭やベランダも淋しい感じですが、クリスマスにちなんだ花の話題を紹介します。12月の主役の植物は、クリスマスツリーとヒイラギです。ヒイラギは日本でも様々な言い伝えがあり、生活に定着した植物です。
クリスマスツリー

クリスマスに欠かせないものと言えば、クリスマスツリーがあります。12月に入るとクリスマスツリーを飾る家庭も多いのではないでしょうか。クリスマスツリーは、「知恵の樹」の象徴と言われ、用材にはモミの木の幼木が用いられます。日本ではアメリカのように実際に木を買って飾り付けをすることはほとんどありませんが、アメリカでは、年間数千万本もの生木のツリーが流通しているそうです。日本では、プラスチック製の常緑樹に似せられた緑色のクリスマスツリーが一般的です。また、雪を被ったように似せた白いクリスマスツリーもり、ホワイトクリスマスを連想させます。選ぶ手間を省くため、オーナメントもツリーとセットにして一緒に販売されていることが多くあります。
O.クルマンが書いた『クリスマスの起源』によると、中世の聖夜の降誕祭の舞台劇で、禁断の木の実を飾るための木として、落葉樹のリンゴの木の代わりにモミの木が使用されたのが由来と書かれています。
家庭でのクリスマスツリーには、オーナメントで飾り付けをしますが、一部では意味を持っているものもあります。ツリーの先端には、キリストの降誕を知らせたベツレヘムの星にちなんで大きな星を飾りますが、天使を飾る国もあります。金色や銀色のボールのようなものは、オーナメントボールと言い、アダムとイヴが食べた知恵の樹の実であるリンゴを象徴しています。また、ツリーの枝には電飾を飾りますが、昔はロウソクを灯していました。現代は豆電球からLEDを用いたものもあり、電飾の色別で点滅したり、音楽に合わせて点滅したりするものもあります。
この他に、キャンディケインと呼ばれる杖の形をした飴やお菓子、雪を模した綿、雪の結晶を形取った装飾などを施します。
欧米では、都市の中心部のスクエアなどに大きなクリスマスツリーが飾られますが、日本では、ビルの灯りを使ってクリスマスツリーを表現したりして、クリスマスを祝います。
ヒイラギ

晩秋から初冬にかけて花を咲かせ、キンモクセイに似た香りを漂わせるヒイラギ。葉の縁がギザギザになっており、その先は鋭い刺のようになっているので、うっかり触ると痛みを感じます。昔からこのギザギザが邪気を払うとされており、庭木などによく使われています。家の庭の北東(表鬼門)にヒイラギ、南西(裏鬼門)にナンテンの木を植えると気門除けとなるとも言われ、また、節分の夜にヒイラギと鰯の頭を門戸に飾ると悪鬼を払うというおまじないもあります。また、クリスマスリースに使ったり、クリスマスカードに描かれたりするヒイラギもありますが、これはセイヨウヒイラギで、日本のヒイラギとは種類が異なります。セイヨウヒイラギも、冬に緑の葉と赤い実を付ける植物であるため、ヨーロッパでは不死の象徴とされ、キリスト教以前から祭事に用いられてきました。先のとがった葉が十字架で処刑されたキリストの冠のイバラを表し、赤い実はキリストの血を表すことで、キリスト教のシンボルになりました。そのためにクリスマスでもヒイラギを用いています。
低木で常緑広葉樹のヒイラギは、幹が堅く、しなやかさを持っており、外からの衝撃や病虫害に強いため、庭木以外にも生け垣として利用されます。また、生け花や盆栽などにも多く用いられ、その特徴的な葉の形は人目を引きます。
日本と西洋で種類の違いはありますが、冬の植物としてこの時期にお目にかかることが多くなります。








